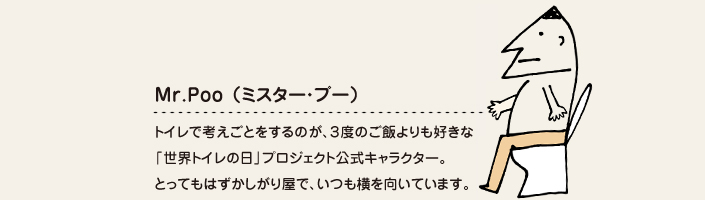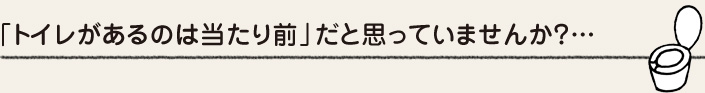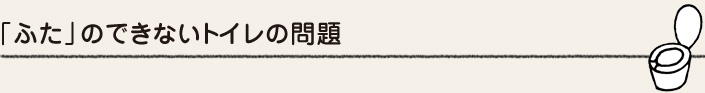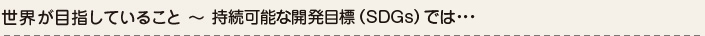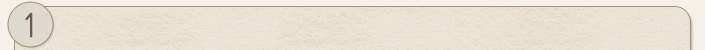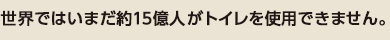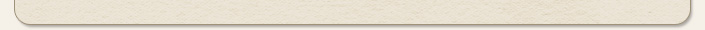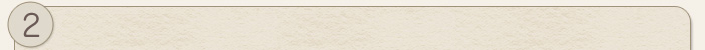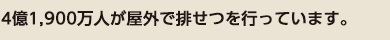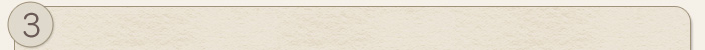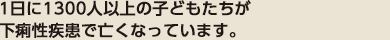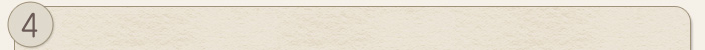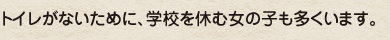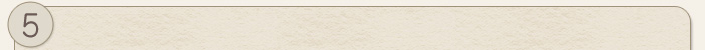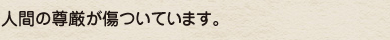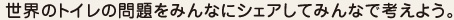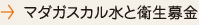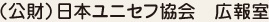世界ではいまだ、3人にひとりがトイレを使えない現実があります。
トイレがない人たちは、バケツやビニール袋にうんちをしたり、屋外で排泄をしたりしているのです。
うんちには、病気を引き起こす細菌がたくさん含まれています。トイレがないところでは、細菌たちがさまざまな所から体内に侵入。それらが原因で、免疫力の弱い子どもたちは下痢を発症し1日に800人以上が、命を落としています。
そんなトイレにまつわる問題を、世界のみんなで考え、少しでも改善していくために。
2013年、国連は毎年11月19日を「世界トイレの日」(World Toilet Day)と定めました。
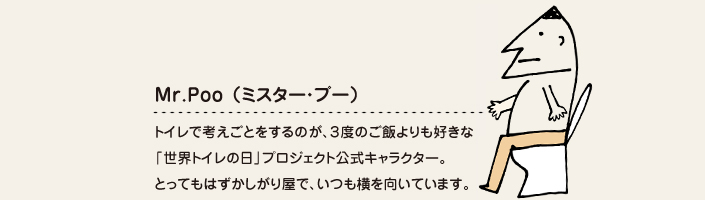

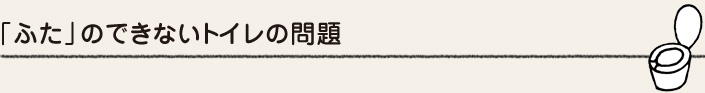
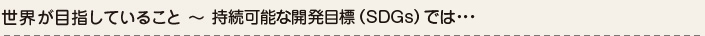
- 目標7
- 2030年までに、すべての人が安全な水とトイレを利用できる状況を実現し、その持続可能な管理を確立する
トイレに関する主なターゲット
- 女性・女子などのニーズに特に配慮しつつ、すべての人のトイレへのアクセスを達成し、屋外排泄をなくす

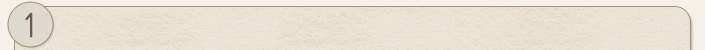
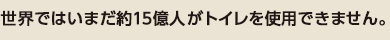
過去20年ほどの間に、トイレを使える人たちの割合は、少しずつ増加してきました。1990年には49%であったその割合は、2015年時点、68%まで向上。しかし、ミレニアム開発目標で掲げた「2015年までにトイレを使える人の割合を75%にする」という目標には届いていません。

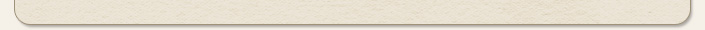
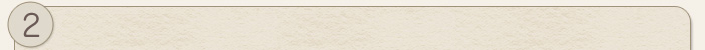
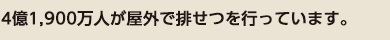
世界ではいまだ、道ばたや草むらなど、屋外で用を足す人々が大勢います。そのうちの約9割が、農村部で生活を営む人々です。屋外排泄をすることによって、排泄物に含まれる病原菌が人の手やはえなどの虫、川、地面などを介して人の口に入り、下痢やかぜなどの病気をひきおこします。
© UNICEF/INDA2008-00043/Ferguson
屋外で排泄するインドの子ども
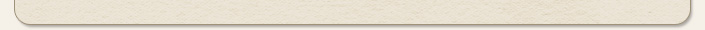
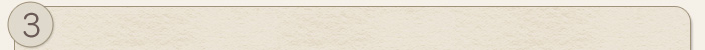
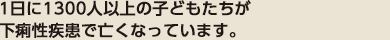
不衛生な水や、トイレ以外の場所での排泄などが原因で、うんちに含まれる細菌が体内に侵入。下痢などの病気を引き起こし、命を落としてしまうことも少なくありません。
© UNICEF/NYHQ2003-0196/LeMoyne
下痢性疾患のイラクの子ども
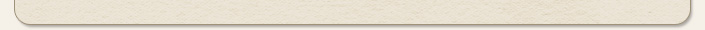
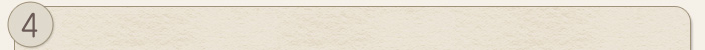
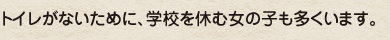
「用を足している姿を人に見られるかもしれない」不安は、特に思春期を迎えた女の子には切実な問題です。また、学校を休むうちに授業がわからなくなることもあり、トイレは教育にも大きな影響を及ぼします。実際にユニセフの報告では、アフリカの女の子の10人にひとりは、トイレがないという理由から生理中は学校を休んだり、退学してしまうという調査結果もあります。
© UNICEF/MLWB2012-01630/Nesbitt
女子トイレの前で微笑むマラウイの女の子
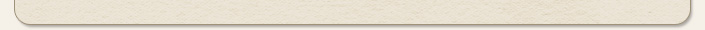
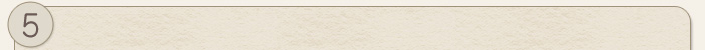
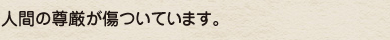
誰でもトイレをしている姿は、人には見られたくないものです。清潔なトイレで人目に触れず、安心して用を足せる環境づくりが、一人ひとりの尊厳を守ることにつながります。
© UNICEF/NYHQ2006-2160/Cranston
避難民キャンプ内のテント型トイレの前に立つスーダンの子ども
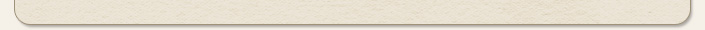
出典元 : 「衛生施設と飲料水の前進:2014」(Progress on SANITATION and DRINKING-WATER 2014 UPDATE)
(日本語要約:2014年5月8日 ユニセフ・WHO 水とトイレの最新報告書を発表)
UNICEF Data
世界子供白書2016


世界では、今なおトイレの不足をはじめ、「手洗い」などの適切な衛生観念や習慣が普及していないために、毎日 800人以上の幼い子どもたちが、下痢などの予防可能な病気で命を落としています。そんな世界の問題を少しでも改善していくために。ユニセフは、国連機関の中でも、特に「水と衛生」の分野において、様々な活動を行っています。
1946年に活動を開始して以来、これまで世界中でトイレの作り方を伝えたり、トイレづくりに必要な資材を届けてきました。また、トイレの後の手洗いの普及など、衛生的な生活についての知識を広める活動も展開しています。
ひとりでも多くの子どもたちが、清潔なトイレを使い、健やかに成長できるように。
ユニセフは、これからも世界各地で衛生習慣や衛生設備の普及をすすめ、衛生に関する問題の解決に取り組んでいきます。



ユニセフ「世界トイレの日」プロジェクトは、これらのサポーター企業とボランタリースタッフの協力のもと、運営されています。


- なぜ11月19日が「世界トイレの日」になったのですか?
- 2001年11月19日に「世界トイレ機関(WTO: World Toilet Organization)」が創設され、「世界トイレサミット」が創設されました。それにあわせて「世界トイレサミット」を開催。その日を記念して「世界トイレの日」が誕生したのです。翌年以降も、毎年11月19日にはトイレの問題を考えるイベント・取り組みが世界各地で開催され、その広がりを受け、2013年7月24日の国連総会で「世界トイレの日」が正式に制定されました。
- トイレが使えるように協力できる方法はありますか?
- 日本ユニセフ協会では、水と衛生(トイレならびに衛生習慣)を普及するために、以下のような募金をお預かりしています。
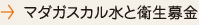
アフリカ南部の島国マダガスカルで、小学校でのトイレや給水設備の建設、衛生教育のために役立てられます。